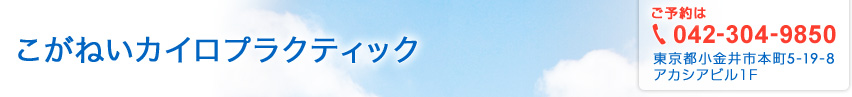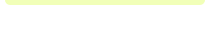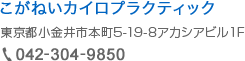7月19日 ぎっくり腰の原因から考える予防
突然襲いかかる「ぎっくり腰」はとても痛く辛いですよね。痛みの原因はさまざまです。腰の中の動く部分(椎間関節、仙腸関節など)や軟骨(椎間板)に許容以上の力がかかって損傷したような状態(捻挫、椎間板損傷)、腰を支える筋肉やすじ(筋肉・腱、靱帯)などの柔らかい組織(軟部組織)の損傷などが多いと考えられますが、これらの原因に共通に考えられる現象にクリープ現象というのがあります。
クリープとは何か?
伸び縮みする弾力性のある組織は、本来は両端を引っ張って伸ばしても引っ張るのを止めれば、また元の長さに縮んで戻ります。ところが一定の長い時間をかけて伸びた状態を持続させていると、引っ張ることを止めても元の長さには縮みにくくなり、ゆるゆるの状態になってしまいます(元に戻るのに時間がかかってしまう)。この現象を素材系の工学的用語で「クリープ」と言います。
ここで言う弾力性のある組織とは、人体で例えると、関節の動きを制限して安定させる「靭帯」、関節を包んでいる膜組織「関節包」、筋の表層に存在する「筋膜」、背骨のクッションになる「椎間板」といったものがこれにあたりますが、こういった組織でクリープが起こることがぎっくり腰や腰痛の共通の原因として有力だと言われています。
ぎっくり腰はなぜ起きるか?
ぎっくり腰をやってしまう時は、何か物を持ち上げようとしたとき、腰をねじるなどの動作をしたときなどに起こるというイメージですが、朝起きた直後や本人の自覚としては「特になにをしたわけでもない」のに起こることもあります。要するに必ずしも無理な動作をした時とは限らないということですが・・・何故でしょうか?
これは腰回りの靭帯や関節包や椎間板にクリープが起きていたら?と考えると説明がつきます。ぎっくり腰をやってしまったその時では無く、その前やあるいは前日に腰を丸める動作の反復や持続を行っていたとすれば、腰の周辺の靭帯がクリープ現象でゆるむことで、関節は不安定になり、不安定になった関節のセンサー(関節の位置や動きの方向、スピードを感知するセンサー)が正常に働かなくなり関節の機能障害がおこります。さらにそれを安定させようとして腰の筋肉に過剰な緊張が生じたり、椎間板の後方が開いて裂傷が起こりやすくなることで、無理な動作でなくても損傷が起こりやすくなってしまいます。そしてこの関節機能障害そのものがちょっとした動作による強烈なぎくっとした痛みを発生させてしまいます。
原因から考えるぎっくり腰の予防
クリープがぎっくり腰や腰痛の原因と考えると、その予防もわかりやすくなります。
長時間腰を丸めて座っていたり、車の運転、草むしりなどのしゃがみこんだ作業などを長時間持続することは、腰の靭帯や椎間板にクリープを起こさせてしまいます。したがって「丸まった姿勢で長時間座らない」「車の運転もまめに休憩をとる」あるいは「座る場合は腰の後ろにクッションやタオルを折りたたんだものを入れて座る」「しゃがみ姿勢や腰を丸めた作業を行っている場合は、まめに立ちあがって腰を伸ばす」。といったことで、ぎっくり腰はもちろん、慢性的な腰痛の予防にもなります。
今年はいよいよ規制の無い夏休みで海水浴やハイキング登山、バーベキュー、花火大会などのイベントも多くなると思います。帰省による車や新幹線での長時間の座り姿勢や、実家で畳の上で過ごすことによる長時間の胡座など、腰を丸めるシチュエーションにあふれています。また在宅で自宅にいる方も腰を丸めて座っていたり、草むしりや部屋の掃除で長い時間しゃがんでいたりすることも多いと思います。ぜひ腰を丸めっぱなしにしないように注意してぎっくり腰や腰痛を予防してみて下さい。
それでもぎっくり腰になってしまったら
武蔵小金井駅近くの整体カイロの当院へ
参考
脊椎のリハビリテーション 臨床マニュアル エンタープライズ
カイロプラクティックテクニックマニュアル エンタープライズ
AKS療法Finalセミナー資料